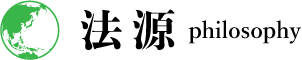第2章
絶望からの再起
──自らの役割を果たすために──
獄中でも私の修行は続いていた
私の入獄はもはや避けられないように、事態は推移しておりました。
しかし、獄舎につながれるということも、大きな意味では天意なのです。獄舎につながれたら獄舎にいる人々を救え、というのが天意です。獄舎でも迷える人を救うことを使命として私は頂いたのです。
もちろん、囚人の身で布教も伝道も行うことはできません。ただ、真実の宗教人の生き方を身をもって示すことしかありませんでした。
私は塀の中の人たちを迷える衆生となんら変わりのない人間としてとらえ、偏見をもたずに接することにしました。
塀の中にいる人たちも、私がマスコミで叩かれたり、ワイドショーでおもしろおかしく取りあげられたりしていたのを知っている人もいました。そんな人たちのなかには、興味本位で近づいてくる人もいれば、出所後に一緒に仕事をしないかと、いかがわしい商売をもちかける人もいました。どんな気持ちで私に近づいてくる人でも、少しの偏見も私情も交えず、宗教家としての真摯な生き方を見てもらうようにしました。
「私は親不孝者です」
私に訴えた囚人がいました。
刑務所に入るくらいですから、親を泣かせたのは当然です。
「私は詫びのしるしに出所したら母親に親孝行をしたいのですが、刑期が満了するのはまだまだ先の話です。そう思うとつらくて……」
囚人は目に光るものを浮かべて私に言いました。
「親孝行というのは、いまからでもできますよ。親孝行は形だけのものではありません。大切なのは人の幸せを願うことです。いつもいつも、その人のことを思うことが大切なのですよ。お母さんのことを思い続ければ、あなたの思いはお母さんに届きます」
「願いや祈りは届くものですか?」
囚人は真剣なまなざしを私に向けました。
私は目に万感の思いをこめてうなずきました。
それから数日後、運動時間のときに私のそばにやってきた囚人は言いました。
「今朝も、母のことを思いました」
満面の笑みを浮かべたすがすがしい表情をしていました。
私は、少なくとも母についての苦しみからはこの男は救われていると思いました。
「よかったねえ」
私は言葉をかけてから思わず鳴咽をかみ殺しました。その1年前、母を私は服役中に亡くしたのです。
私は刑務所で一時期、衛生係という役務についていたことがあります。これはわりに大変な仕事なのですが、宗教家である私にとってはまたとない修行の場所でした。体に不調のある人や老人受刑者、持病のある囚人などの世話をする役目です。刑務所の中も
そういうときも、決して不快な顔、汚いというような表情、めんどくさいような素振りにならないように気を配って接しました。私はいかなるときも、人類救済の修行をしているのだということを忘れずにいようと心に決めていました。
ある老人の受刑者の下着を取り替えているときに、彼はくぼんだ目を私に向けて手を合わせたのです。
「あなたはほんとうに神様のような人じゃのう」
そう言って頭を下げました。
一瞬、冗談を言っているのかなと思いました。なぜなら、塀の中での私のあだ名は「神様」でした。しかし、その老受刑者は冗談を言っているようではありません。
私のあだ名の「神様」は、もちろん私が宗教家であることを知っていて、囚人たちはからかいのニックネームをつけたのです。私は、そんなことを意にかけてはいませんでした。しかし「あなたは神様のような人だ」と老囚人に言われたときは、心の底から自分の生き方をふり返りました。そして「人のために生きたい」と願いました。
老人をいたわる私も、決して若い年齢ではありません。いうならば、私も老齢で「老老介護」のようなものです。決して私も体力のある身ではありませんが、老いに苦しんでいる受刑者に少しでも温かい手を差しのべることが、これ、真の修行ではないかと私は考えたのです。私は神ではありませんが、少しでも人の役に立ちたいという思いで日々過ごしていたのです。
衛生係というのは食器洗いなど、水を使うことが多いのです。そのために、あかぎれになるのはしばしばでした。
私は、その手にいつも「
「何しているの?」
私が手をさすっていると、声をかけてくる囚人もいました。見た目はあまりにも痛々しいので、気の毒に思ったのでしょう。
「医務科に行って薬をもらってきたほうがいいよ」
アドバイスをしてくれる者もいました。暖房のない刑務所では凍傷になる人も多く、医務診察の際に凍傷の軟膏を出してもらって手当をしている囚人が多かったのです。私は周囲からすすめられたが、一度も薬を使わず、「
刑務所の中で私は布教も伝道もできませんから「
「もちろん、痛みはありますよ。しかし、こういう環境だからこそ薬に頼らないで治すことを心がけているのです。ほら、このようにしてさすっていると、痛みが少しずつ和らいで傷口がふさがってくるのです。見た目ほどつらくはありませんから、ご心配はいりません」
私は、天のエネルギーをわが身に通す
私が受刑者に接してきた思いは「真に救われなければならないのはあなたたちですよ」という思いでした。社会通念上からいえば、私も罪人です。罪人のくせに他人を救うなど、えらそうなことをいうな、と思われる方もいらっしゃるでしょう。しかし、私には天の指示によって、どこにいても救いの手を差しのべなければならない人がいるのです。天は、獄舎につながれている私に対して、どこに行っても修行せよ、迷える人に対しては救いの手を差しのべよと命じたのです。
私はその聖なる声をしっかりと受け止め、その声に動かされて暗い獄舎につながれたのです。
そして私は「逆境にある者にとってこそ天声が必要であり、逆境にある者を救えない宗教は単なる気休めでしかない」ということをあらためて痛感したのです。
私は、獄舎につながれた15年の間を一日たりとも休まず、迷える人を救うという宗教的使命を一身に受けて修行を続けていたのです。