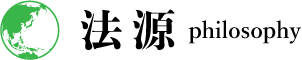第4章
人がよろこぶ行為は自分のよろこびとなる
──他人の痛みは自分の痛み──
貧者の一灯について考える
金銭というものの考え方はとても難しいのです。
現代社会ではお金がないと暮らしていけないのですから、とても大切なものであることは判ります。
ところが、お金によって人生が狂ってしまう人もいるのですから、ある意味で、金銭は魔物のように恐ろしいものといえないこともありません。
「カネは邪魔にならない」などという言い方もあります。お金は、あればあるほど好都合だということです。金銭は使い道があって、いくらあってもこれで十分ということはないという意味にもとれます。
しかし、金銭は人間の欲望の象徴のようなもので、金銭で身を誤るということはよくある話です。金銭で人間性ががらりと変わってしまうという例などは、よく見聞することです。
貧しいときには純朴で思いやりのあった人が金持ちになって粗野で傲慢な人柄に変わったという話は、よく見聞する例です。金によって、真実が見えなくなったわけです。
金銭がないときには仲のよかった兄弟が、親の遺産が転がりこむようになってから、急に
宗教的な考え方としては、金銭は持ちすぎないほうがいいということになっています。金銭がありすぎると世俗の暮らしに執着が強くなって、禁欲、忍耐の思いが少なくなって修行の妨げになるからです。
仏教やキリスト教では、富める人は、貧しい人に対して富を分配することで功徳や徳を得られると考えられています。
布施や寄進や慈善バザーは、己の富を貧しい人たちに恵むという美しい心根が「神」の心にかなうということで行われています。
「喜捨」という言い方があります。文字どおり、よろこんで貧しい人や神仏に施しをするということです。よろこんで捨てるというところに価値があります。
人に施しをするのに嫌々ながら施しをしても、功徳にはなりません。よろこんで捨てるところに価値があるのです。
現代人は、同じ価値のものを嫌々捨てようが、よろこんで捨てようが、受け取る側の重みは同じではないかと考えます。合理的価値からいえば金銭の利用価値は同じです。ところが、宗教的にはまるで違います。
人に物を施すという行為は、宗教的にいえば、いかに自分が「欲望」や「犠牲」を超えて他者を思いやることができるかという心の修行でもあるわけです。
大金持ちが百万円を寄付するより、それほど裕福ではない人が一万円を寄付することが功徳が大きいわけです。
宗教的な寄付は、金銭の価値ではなく心の価値が問われるわけです。
貧者の一灯というのは、富むものが寄進する万灯より、貧しいものの寄進する小さな一灯こそが功徳が大きいと教えています。
すなわち、金持ちの莫大な寄付より、明日の糧を得ることさえままならない、貧しい人の小さな喜捨が尊いと教えているわけです。
他人への施しは、自分が苦労して行うことで功徳が大きくなるということです。席を譲るのも、「ああ、せっかく座ったのに、この席を譲るのがつらいなあ」という気持ちではなく、「たしかに自分も疲れている……それでも、この老人を座らせてあげよう」と気持ちを強くもって席を譲ったときに功徳が大きくなるのです。
楽を求める心に打ち勝って自分は苦を背負い、少しでも人に楽を与えようとする心が人助けの基本なのです。
自分の気持ちは暗く、とても他人に笑いかけたりするゆとりはない。しかし、この人に笑顔を向けることが、この人のかすかな救いになるのだと判断したとき、無理にでも微笑みかけるということが笑顔の布施なのです。
他人がよろこぶ姿こそが自分のよろこびということを知ることで、充実した人生を送ることができるのです。
ただし、自己犠牲のところで述べたように、気がついたら自然にやっていたというのが、本来の価値ある布施です。人からよく思われたくてやる布施は、自分のための布施で、苦の