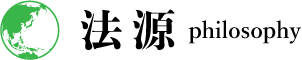第4章
人がよろこぶ行為は自分のよろこびとなる
──他人の痛みは自分の痛み──
自分が犠牲になれば、そのぶん、人は救われる
私が再起のためになさなければならないと考えたのは、徳積みということでした。なぜなら、人類救済の原点が徳積みだからです。
人をよろこばせるということは救済の基本形です。
徳積みということを、あらたまって考える必要はないのです。人がよろこぶことをこの身を使って行うこと、というふうに気楽に考えることです。
重い荷物を持ってよろよろと歩いている人がいれば、その荷物を持ってあげることも、広い意味では徳積みの一つです。
私自身、70歳に手が届く歳になり、加えて長い刑務所暮らしで足腰が不自由になってきているので、若い人と同じように力仕事のお手伝いを身軽に買って出るということはできません。しかし、人のために役に立ちたいという気持ちだけは失わないようにしたいと思っています。
先日も近所に所用で出かけたおり、年をとった女の人がスーパーの買い物袋を重そうに引きずっているので、少しお持ちしましょうと言って、ほんの百メートルばかり、荷物を持ってあげました。
後ろ姿が母親に似ていたので、おもわず声をかけてしまいました。母親は、私が刑務所につながれている間に他界してしまいました。おもわぬ運命の激変で、死に目にも会えなかったものですから、母親のことを思うと、こみ上げるものがあるのです。
後ろ姿は母を思わせる姿形をしていましたが、お顔は母とはまるで違っていました。荷物を持ってやるといっても、ほんの信号の一区間だけのお手伝いでした。
別れるときに、ご婦人から「おいくつになりました?」と聞かれました。「もうすぐ70歳です」と答えましたら、「あらいやだ、私のほうが年下ですわ」と女の人は顔を赤らめて恐縮していました。助けたつもりが恥をかかせた格好になり、逆に申しわけのないことをしてしまいました。年寄りの冷や水ではありませんが、老人が力仕事なんか手伝ったりすると、かえって相手に気を遣わせてしまいます。しかし、相手のためになることをしようという気持ちは、いくつになっても失いたくないものです。
人助けは、なにも力仕事だけではありません。困った人の話を聴いてあげる、話し相手になってあげるというようなことなら、年をとっていても可能です。いまとなっては私は体があまり丈夫ではありませんが、人のために役立つことをすることを再起の第一歩にしたいと考えています。
昔の行者の方より、ぜひ話を聴いてほしいと頼まれ、いろいろと相談を受けました。体調のあまりいいときではなかったのですが、私はあえて時間をつくってお目にかかりました。
人生相談というような重い話ではありませんでしたが、だれかに胸にわだかまる話を聴いてもらいたかったようでした。私が話を聴いてあげることで、その方の心は少し晴れたようでした。ほんの小さなことですが、人の役に立つことができたことに、私はこの上ないよろこびを感じました。
人間は本来、よろこびを表現するために生きているのです。
「功徳を施す」という言い方があります。直接的には仏に対してよいことを行うことですが、その根本的な目的は、功徳を行うことによってよい報いを頂くためです。
すなわち、人がよろこぶことをすれば報いとしてよいことがわが身に降りかかるのです。「よい報い」を「よろこび」という言葉に置き換えることもできます。
すなわち、人のためによいことをなせば、自分にはよろこびが返ってくると考えることもできるのです。
人に尽くせばよろこびが返ってくるなどといいますと、お中元やお歳暮のお返しみたいですが、徳積みは形ある見返りを求めないということが正しいのです。徳積みとは、そういうものです。自分の行為を金銭と交換するのは徳積みではありません。
「布施をする」という言葉もご存じと思います。仏に対しての功徳の一つです。金品を仏に捧げることを一般的に布施といいます。しかし、必ずしも仏に対してではなく、また金品でなくとも布施の心にかなうのです。
たとえば、電車でお年寄りに席を譲るのも布施の心です。混んだ電車の中で自分が立って、体の弱い人や老人に席を譲るという行為も布施の心です。前述のように、他人の荷物を持ってあげるという行為も布施の心です。
人に笑顔を向けるのも、広い意味では布施の心です。道に迷い途方に暮れている人に一夜の宿を提供するのも、布施の心です。布施の心に決まりはありません。ただ根底に流れているのは、自己を最大限に使って相手に尽くすということです。
自分が犠牲になれば、そのぶん、他人が幸せになるのです。犠牲の大きさに比例して、よろこびが大きくなるのです。
ただし、ここでいう自己犠牲は、本人は犠牲になっていると思っていなくて、気がついたら、勝手に