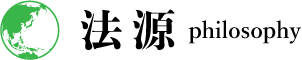第4章
人がよろこぶ行為は自分のよろこびとなる
──他人の痛みは自分の痛み──
他人の痛みを知る人とは
人間には知性があり、基本的には他者の幸せを願っています。
他者の幸せというより、自分も幸せでありたいし、他人にも幸せになってほしいという共存共栄を望んでいます。平均的な市民の多くは、自分の幸せはもちろん、みなが幸せであり、かつ世界が平和であることは望ましいことだと考えているはずです。
ところが、別の見方もあります。現代は、自分がよければ他人には無関心という人が多いということです。たしかに、現代は利己的社会と見られています。他人の幸せより、まず自分の幸せのほうが大切と考えている人が多い時代です。
ある意味で、それもしかたがない部分があります。なにしろ、人間というのはなによりも自分が可愛いというところがあります。
しかし、自分だけに愛着をもっている人は、リーダーにも会社の上司にもなれません。たとえば、スポーツチームの監督や主将にもなれません。もちろん、実生活においても、工事の現場監督にもコンビニやスーパーの店長にもなれません。まして、一国の進路を担う、政治家や首相が自己中心的であれば、国の針路を誤らせてしまうことになりかねません。利己的な人はリーダーとしては失格です。
頼れるリーダーとは、相手の身になって物事を考えられる人です。相手が何を悩んでいるか、何に苦労しているかを解って一緒に考え、一緒に苦しむ人がリーダーの素質がある人であり、リーダーとして資格のある人です。
強いチームなどで、よく鬼監督などと呼ばれる人がいます。練習に厳しく容赦なく結果を求めてくる監督です。しかし、たんに技術を向上させるために非情の訓練を強いる監督であれば、決してチームの力は強くならないし、いい成績を残すことはできません。人間の心をもたない鬼監督では、人はだれも命令に従いません。
部下や部員やチームの選手の求めている心情を理解し、それをふまえたうえで相手を導くという人こそが名リーダーであり名監督です。名監督というのは、たんなる鬼監督ではありません。厳しいだけでは、真のリーダーとはいえません。
名実ともに名監督といわれる人は、選手の痛み悲しみ、もどかしさ、焦りなど、いろいろな心的状況を把握して、それを心に秘めて選手に向かいあっているのです。ゆえに、選手は激しい罵倒も苛酷なしごきにも耐えて、どこまでもついていくのです。
「あの人は苦労人だ……」という言い方をします。文字どおり、人生の道程を苦労して生きてきた人のことです。貧しさを経験してきた人は、貧しさのなかで生きる人の気持ちがよく解ります。下積みを長い間経験して出世した人などは、働く社員の心をよく解っています。下っ端の悲哀も、みじめさもよく理解しています。自分がかつて体験した苦しみだからです。
苦労してのし上がった人は、名もなく貧しくこき使われてきた人の悲哀をよく知っていて、そのつらい気持ちを知ったうえで部下を使うので、部下は心を開いてついてくるのです。
二代目社長、二代目代議士がよく失敗することがあります。苦労知らずで、のし上がったからです。嵐の日を知らないで、嵐のなかを生きぬくことはできません。なんの苦労も知らない二代目では、社員の心も得意先の人情の
二代目が失敗するのは、創業の苛酷な苦労を知らないで、家業を継ぐからです。苦労しないで手にした地位ですから、失敗することが多いのです。
もちろん、二代目のなかにもすぐれた人がいて、創業者よりも会社を大きくした人もいないではありませんが、一般的に苦労人と呼ばれるような二代目はいません。
人生のつらさを知っているから、人に慰めの言葉をかけたり、いたわったりすることができるのです。苦労人は、自分でつらい思いをしたことは人には経験をさせたくないというので、他人には思いやりの心で接します。それで苦労人は人望が厚いのです。苦労人の上司は部下に慕われます。
もちろん、人間を救済する宗教家は人間をよく知らなければなりません。自分が苦労しないで真の救世主にはなれません。偉大な宗教家は地獄の修行に耐えぬいて、この世は苦の世界であることを悟ったのです。
釈迦は周知のように王家の出で、なに不自由なく暮らしていましたが、天才的な哲学家で、若くして、この世が苦悩に満ちていることを感じたのです。
釈迦はなぜ幸福な身分を捨てて苦行の出家を選んだのか、有名な四門出遊の故事が伝えられています。
あるとき、釈迦の父が治めている領土の東門で、釈迦は老人に出会いました。よぼよぼした老人でした。この人にも華やかな若い時代があったのにと釈迦は胸を痛めました。南門を出るときに、病に苦しんでいる人に出会いました。この人はこの間まで健康だったのにと考えると、釈迦はつらい気持ちになりました。西門で、道ばたにうち捨てられている死者を目撃しました。この身も、これらの人々となんら変わりはなく、生・老・病・死の苦しみから逃れられない宿命にあることに釈迦は気がつきました。釈迦は、この苦しみから逃れるにはどうしたらいいかということで真剣に悩みました。
釈迦は幼いころから、城の楼台から外を眺め、苛酷な使役に苦しんでいる奴隷たちの姿を見て、この世には自分のような裕福な家に生まれる者と、奴隷のような境涯に生まれる者とがいるのはなぜなのか……どうして人間には不公平な現実があるのだろうか、という不条理に悩んでいました。
出生の不条理に加えて、逃れることのできない生老病死の苦悩に目ざめた釈迦は、真剣に救われることを求めました。
ある日北門で、一人の出家に出会いました。世俗の苦しみから超越したようなすがすがしい出家者を見た釈迦は、自分も出家して修行し、悟りを開きたいものと考えました。ついに釈迦は29歳のとき、妻や子どもを捨てて真夜中に王宮を出奔しました。城を取り囲む東西南北の四つの門で、釈迦は偉大な教祖への道へ駆りたてる疑問に直面しました。この故事を「四門出遊」と呼んでいます。
出家した釈迦は死の直前に至るような荒行に挑み、なんとか苦悩を脱出しようとします。数々の行をくぐり抜け、「人を救いたい」では、救えないことを悟ったとき、いま、このままで、よろこんでいる自分に目ざめ、ついに菩提樹の下で無常の真理に開眼しました。
しかし、道を説こうにも、どのように布教していいか解らなかった釈迦は、昔の5人の仲間たちと伝道の旅に出るのです。
愛する妻子と別れた苦悩が「会者定離」(この世で出会ったものは必ず別れる)の真理を導きだしたり、自分が生まれた王家の一族が戦で滅ぼされるなど、つらい体験を経ることで「生者必滅」や「諸行無常」の真理を人々に伝えることができたのです。
世俗の
その痛みを理解するだけでいいのです。
「あなたは、かくしかじかのことで悲しんでいるのですね。よくわかります。私はなにもしてあげられませんが、せめて一緒に泣くことはできますよ」
このような気持ちをもって人に対することはできます。その思いをもつことが大切なのです。その気持ちをもって人に対するかぎり、あなたは多くの人に慕われ、すぐれたリーダーの素質をもっている人ということになります。