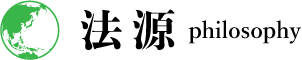第5章
人間の絆こそ心のエネルギー
──美しき情の世界──
母の愛は心の栄養素
子どもの虐待があとを断ちません。他人が虐待をするのではありません。親が自分の子どもを虐待するのですから、救われない気持ちがいたします。
母性愛、父性愛という言葉がありますが、親というのは子に対して特別の愛情をもっているはずです。血肉を分けた分身ということもあり、親の愛は本来、本能的なものであり理屈ではありません。理屈ぬきにわが子を愛するのが親です。
出来がいい子であれば親は、親ばかと見えるほどに子を誇りに思い、出来が悪い子であれば、出来が悪い子ゆえに、いっそう身が案じられて可愛いのです。出来がよくても悪くても、無条件に子を愛しく思うのが親心です。
私は人生のいろいろな局面で危機に立たされたり、非難の矢面に立たされたことがあります。周囲の人間がみんな離れていき、まったくの孤立無援になったことが幾度となくありますが、そのときでも母親は私を信じて励ましてくれました。私が無言で泣いているときは、そっと涙を拭くハンカチを私の手に握らせてくれました。おそらく、そのときの母親の心境は、わが子だから信じ、わが子だから見放してはいけないという親心だったと思います。世の中の人がすべてお前を見放しても、私だけはついていてあげますからね。それが母の心だったと思います。
ある著名な女流作家は「母の勤めは、もし子どもが刑務所に入って帰ってきたら、なにもいわずに抱きしめてやることぐらいなもの」となにかの書物に書いていました。すなわち、人生の一番つらくて悲しい局面に母の出番があるということです。母には本能的な愛があるゆえに、それが可能なのです。母の愛はほとんど、仏の愛に近いものがあります。しかし、仏でさえも母親にかなわないのは、母親の愛が理屈ではないということです。
私の母は、私が服役中に亡くなりました。どんなときでも、なにもいわずに私を無条件に包んでくれた母は、もう、この世におりません。厚い壁に阻まれた獄中で母の死を知らされ、外に出てみると母のいない空間がどこまでもむなしく果てしなく広がっていました。これは、私にとりまして、たまらなく悲しいことでした。
70歳に手の届く自分が、母親に手を引かれている子どもを見ますと羨望の思いにかられます。「ああ、あの子には母がいる……」という思いです。それと同時に、その子がこの母の愛を生涯失わないようにと心の底から想わずにはいられません。
親の愛は心の滋養分として欠かせません。
「親は無くても子は育つ」とざれ歌に唄われています。たしかに食べるものさえ与えておけば、子どもは成長していくでしょう。しかしそれは、ただたんに体が大きくなっていったというだけで、心の栄養を十分に与えられた健全な子どもとはいえないのです。親の愛を知らずに育った子どもは、なにか不足しているものがあると思います。
犯罪をおかす少年少女の深層心理を分析してみますと、幼少期に母親に抱きしめられた記憶がない子どもが、非常に高い確率で見られたというのです。
子どもの
母が子を守るという本能は、どこに行ってしまったのでしょうか。