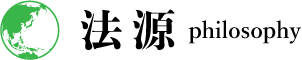第1章
悔恨と懺悔の日々
──天が与えた私への試練──
乱のなかに光を求めて
35年前、私は「乱を求めて生きよ」と自著の中で書いたことがあります。
人生の歩みのなかで襲いくる試練を私は「乱」と名づけたのです。自分が乱のなかに投げこまれたとき、それを避けたり逃げたりしてはならないということを語ったわけです。
「戦いこそ万物の父であり母である」と語ったのは、ギリシャの偉大な哲学者ヘラクレイトスです。乱に遭遇することは、まさにそれは己の内なる戦いであり、乱を乗り越えた者こそ人生の勝者なのです。
乱こそは人間に降りかかる災難であり、苦悩であり、乱と戦い乗り越えるということは、人間の創造や知恵を導き出してくれる万物の父と母に出会うということなのです。
私が獄につながれたのは乱のなかでも最大級の「大乱」でした。このように生涯に二度とは起こらないような投獄というような大きな乱は別として、人間の生涯は乱の生涯といえないことはありません。
作家の舟橋聖一に「花の生涯」という小説があります。
彦根藩の藩主の弟で日陰暮らしをしていた井伊直弼が、思いもよらぬ縁から幕府大老となって、政局の混乱の当事者となり、最後は雪の桜田門外で勤皇浪士に襲われて一命を散らすまでを描いた長編小説です。題名は「花の生涯」となっていますが、まさに、政治の波乱の季節に「乱」のなかで生涯を閉じた男のロマンを歌いあげた物語です。
人間の起伏に富んだ人生は多かれ少なかれ「乱の生涯」といえるでしょう。
私は父親を戦争でなくして女手一つで育てられたことが、まさに私の乱の始まりでした。戦争も乱であり、敗戦も乱です。そして私は乱のなかに誕生したのです。
乱の歳月は続きました。私はどもりというハンディを背負っていたので、幼年期から乱を背負っていたことになります。乱に誕生し、乱のなかで育ちました。
私の青春は暗いもので、まさに乱を地で行く青春期を過ごしたのです。長じて立ち上げた事業に花が咲いたと思ったら嵐に見舞われ、倒産という乱のなかに投げこまれたのです。
そして、ついに私は天声によって生きる道を得ることになったのですが、その私に天はますます苛酷な乱を背負わせたのです。すなわち、人生でこれ以上の大きな乱はないというような「法難」に出会うことになりました。
私は35年前の自著で語っています。
《もし「乱」を経て立ち上がることができなかったなら、それは「乱」ではなく「死」であったことになる。しかし、立ち上がるということは、すぐにでなくともよいのだ。時間をかけて立ち上がってもよい。その自分を支えるもの、自らが立ち上がるためのエネルギーとなるものを見つけることだ》
「乱を求めよ」というのはひとつの比喩で、乱に飲みこまれても自分自身を失うなということです。すなわち、乱を自分を成長させるエネルギーに変えるということです。
私が投獄されて、この世ではない辛酸を舐めました。しかし、私はその苦しみに比例するように、人類救済への
苦しみ、悲しみの試練を天は私の痩せた両肩に耐えがたいほどに乗せたのです。この重さに耐えられるか……。天は私を鞭打っているように思いました。この大乱をくぐり抜けたら偉大な救済者として再生するだろうという天の試練だったような気がします。
私は大乱のなかで光を求めました。私の生きる道を照らす一筋の光を求めたのです。