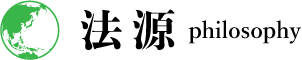第一章 天意
【3】
いまでこそ、みなさんには
それは、わたくし〝福永輝義〟の死ということがいえるだろう。もちろん肉体的な死という意味ではない。かといって精神的な死という意味でもない。35年弱の「私の人生」の死ということができるかもしれない。
絶頂から奈落。その落差は激しかった。35年弱の人生のすべてが、無に帰してしまったのである。なみの落差ではなかっただけに、私の身や心はボロボロであった。まさに自分の人生に終止符を打とうとするまでに、追い込まれていたのである。
それを免れ、新しい人生を歩めることになったのは、私の母のおかげであった。
まず、その母のことから始めよう。
山口県の旧家に生まれた母は、その時代にあっても苦労をせず、親の愛情にも恵まれて育ったという。いわば箱入りのお嬢さんのように、世間の風にあたることのないままに成人したのであろう。
ただし、母には一風変わったところがあった。それを文字にすると、「信仰心」ということで表現できるが、さらに細かくつけ加えるならば、どこまでも純粋で、
そのことを私が子どものころに、祖母に聞かされたのか、あるいは伯父から聞かされたのかはっきりしないが、とにかく私の記憶のなかに、母の逸話がいくつか残っているのである。
母にはひとつの大きな夢があった。それは、ものごころついたころからの、長年の夢であったという。それはなんと修道女になることだった。
当時の社会情勢からは、考えもおよばないことである。国家神道が重んじられ、仏教さえも肩身のせまい思いをしていた時代のこと。ましてや、恵まれた家庭環境から考えたならば、進んで戒律の厳しい環境へ身を置くなどということは、世間知らずのわがままととらえられてもしかたのないことである。
もちろん、異国の宗教を社会が許すべくもない。ただ、母自身のなかに絶対キリスト教でなくてはならないという
では、一種の修道女などに対する憧れかといえば、それも当たらない。憧れというような
母はお地蔵さまにも、お不動さまにも、区別することなく手を合わせていた。すべての神仏を敬い、尊んでいたといえる。しかし、だからといって、母は決して神仏などを「願かけ」の対象にすることはなかった。
そんな母が、戦地へ
それから24年と数か月後、ふりかかった事態の大きさに失望し、私が死を決意し実行しようとした瞬間、はじめての「天声」がつらぬいた。
そして、時を同じくして、母が積み重ねてきた「般若心経」の十万枚写経が達成されたのだった。
昭和55年1月6日午前2時ちょうどであった。
母のお陰で免れたと言ったのは、その不思議な一致である。
行者さんから、「
その十万枚達成について、私は後日、母から聞かされたのであるが、その不思議さもそうだが、親子のつながりを嫌というほど私は強く感じたのであった。別々に生きているように見えても、親子のつながりは、想像以上に強いのである。