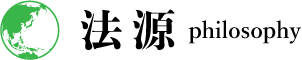第五章 法源
【8】
その後、日本中をバブル経済が駆けめぐっていった。人々は豪華な生活を求め、高級車やブランド商品に群がっていった。
そして、バブル崩壊である。これを契機にして、相談件数は日増しに増えていった。それこそ、朝から晩まで相談者との面談に忙殺されるようになった。そして、だれもがこぞって4泊5日の修行に参加したのである。4泊5日の参加者の動機は、その時代を反映して経済的なものが多かった。
また、この時期から、家族全員で参加する人たちが増えていた。「法の華」の広がりがすそ野を大きくしていたころである。この家族全員の参加は、その家系の根本から問題が解決するという意味がこめられていた。子どもたちは、わけのわからないまま参加していたが、5日目にはみな最高の
また、不思議と頭でっかちの人の参加者が増えていったのも、このころのことである。
そんなある日、参加者の苦労を直接目にする若いスタッフたちから、「
「
といったことである。彼らは「
私は、そのまま要望を天に伺ってみた。すると、
「貧乏人ほど、大きな
と「天声」は答えを出してきた。
この「天声」のいう「貧乏人」とは、金のない人のことではない。いつも金にこだわり、そのことで苦を刻んでいる人のことを指している。いわば
そのとき、私の脳裏に一人のおばあさんのことが想い出されていた。
70歳を越えていると思われるおばあさんが、修行日に
しかし、それはおばあさんの「
滅多にないことであるが、そのときだけはたまたま、私はおばあさんの「
ここにいう「天納」とは、修行を受ける方が決断した尊い「
さて、たまたまそばを通りかかった私は、その場面を目撃することになった。おばあさんは大事そうに「
そのときのおばあさんの満足された姿が想い出される。まるで70年以上も背負ってきた重い荷物を、そこに「よいしょ」と降ろしたような安堵感につつまれていた。それは至福のときであったのかもしれない。やがて笑みがこぼれ、よろこびが身体いっぱいに広がっていく様子がうかがえた。
「ああ、やっぱりこれで良かったのだなあ」
と私自身も非常に満足感を覚えたのをいまでもよく想い出す。もしも、このおばあさんの体験がなかったならば、きっと心のどこかでなにか納得のいかない気持ちを抱いていたかもしれない。
さて、このおばあさんであるが、「天納」を終えると、私に深々と頭を下げて、こんなことを言った。
「定めた瞬間から、足裏がポカポカしてきましたよ」
すでに、このおばあさんは「天納」したときに、頭が取れてしまったようである。私はそう感じていた。高齢者の修行参加がはじめての経験であったために、スタッフのほうがまごつく場面が多かった。しかし、そんな心配をよそに、おばあさんは若い参加者に負けないほど一生懸命に修行に励んでいらっしゃった。
修了日には、おばあさんの曲がっていた背筋がしゃんと伸び、気力も充実して、まるで10歳は若返ったような感じがした。そして、「人生の意味が解けた」と意気盛んによろこんで帰っていかれた。その後も、行をしっかりと繰り返されていると聞いた。