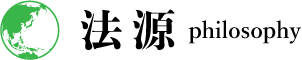第三章 天声
【7】
最高の日々であった。
運営資金では、相変わらず苦労していたが、しかし、人のよろこびが自分のよろこびの日々であった。
そんなある日のこと。
「新聞紙を1万円札の大きさに切り、99枚用意しろ。その上に、ほんとうの1枚を重ねあわせ束ね、封筒に入れて封をしろ。マイクを持つときは、それを背広の内ポケットに入れなさい」
という「天声」が下った。
最初、これを聞いたとき、運営資金に苦労する私を見かねたのだろうか、と思ったくらいである。私は、さっそく、伝えられたとおりにつくってみた。
背広の左ポケットには、「天声ノート」が入っていたので、それを右のポケットに入れてみた。すると、なにかスウスウとしていた胸のあたりが心地よくなった。ほんとうに、ポケットの中にお金があるように感じ、気持ちにゆとりが生まれるのだ。
経営をしていたころ、そのポケットに入っていたのは伝票などだった。それに請求書や領収書の類もまじっていた。当時は、それを少しでも多く渡すことだけを考えて生活をしていた。
ところが、天声のままに計算を捨ててみると、数字でのおつきあいではなく、血のかよった人間同士のおつきあいができるようになっていた。どこの街に行っても、人の真心に迎えられ、温かな歓迎を受けたのである。
私は新聞の入った封筒を胸にしながら、そうしたことが起きていたことをあらためて想い出していた。
まともに考えたならば、新聞紙は新聞紙である。しかし、それは教えこまれてきた固定観念でしかない。世の中に通用するしないは別にして、その新聞紙が自分自身にお金として通用するのであれば、それは札束になるのである。
もちろん、これも屁理屈にすぎない。しかし、お札も新聞紙も紙であることには変わりない。お札と新聞紙に価値観をつけているのは、私たち人間であるというのならば、その私たちの気持ちが変われば、価値観も変わってしまうのである。
いずれにせよ、はっきりいえることは、「お金とはに不思議なものだ」と、つくづく感じることである。