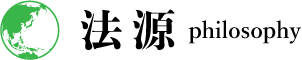第一章 天意
【2】
私は桜が好きである……。
とりたてて特別な想い出があるわけではないが、桜には魅かれるものがある。早朝の人気のない護国寺の境内に立ち、少し遠まきに桜を見あげると、朝ぼらけの景色のなかに、白い上弦の月が、桜の花に染まっているかのように見える。
「春になれば、桜の花は必ず咲く」
ふっと心のなかで呟く。絵心でもあれば、きっともう少し違った表現ができるのであろう。しかし、この16年間(本書初版当時)というものは、「天声」だけを聞き、その実証にまい進してきた私にとって、自分の時間はあまりにも少なかった。
年をとればとるほど、こういう時間がありがたくなってきている。生身の人間としての私にも、このような山水の白い部分が必要なのであろう。人によっては、それは紅葉や海原なのかもしれない。
朝の天行力を終えてきたいま、私の観いは2001年に向かっている。たしかに自身の人生をふり返る余裕すら与えられなかった16年であったが、それでも私は充分に満ちたりている。悔いることはなにひとつとしてない。こうして早朝の桜を穏やかに眺められることに、万感の観いがある。感謝せずにはいられない。
愛用の下駄を素足につっかけ、まだ肌寒い境内をのんびりと散策していると、桜の花びらに重なって、出会った人々の顔が次々と浮かんでくる。思い起こしてみれば、その数はここに開花している桜の花ほどに多数である。
そういえば、先日の「三法行会」にも、古い行者さんが一人娘を連れてきていた。不妊に悩んで修行を受けた方だった。しかし、修行を終えても、子どもを授からない。それでも彼女は1千日間、行を繰り返したのである。
約3年間、ただ繰り返してきたその答えは、まったく「行」に理解を示さなかったご主人が修行に参加したことである。いつも小難しい顔をして、反対のことばかり口にしていたご主人であったそうだが、修行を終えて最高の笑顔を手にした後、しばらくして、彼女は妊娠したのだった。その子ももう、6つだという。
桜の花びらの上に、次々とよろこびの顔が開いていくのが見える。まだ四分咲きほどであるが、すでに満開のようなにぎやかさが感じられる。春のよろこびを精いっぱいに表現する偉大な生命力は、それだけで気持をわくわくさせてくれる。
ありがたい……。その気持ちは素直に、両手を胸の前に合わせさせる。こみ上げてくる最高のよろこびは目頭までも濡れさせる。こうして生きていることの充足感、なにはなくともいま生かされていることのよろこびは、素直に「最高!」という言葉を吐かせてくれる。
「自分を無くしたところに、人生の花が咲く」
これは「天声」でいつも示される言葉である。そのたびに、私自身もまた、その「天意」を新鮮に受け止めることができる。
天意とは……。天意とは何であろうか。
ひとことで言いあらわすならば、人の思考によらない「天」の意思といえるだろう。いまここで開花している桜も、天意である。「天」の意思のままに、最高のよろこびを「いま」精いっぱいに表現しているのである。
多くの人々は、人生に花が咲いているとき、つまり現実に幸せと思える状態が見え、聞こえ、触れることができているときにだけ、よろこびというものを実感する。そして、それは一過性のものであると強く信じているところがある。
そのために、現実の生活や健康に悩み疲れ、あるいは毎日の生きる張りというものを見失ったときに、そのような人たちは、まるで想い出のなかにのみ「よろこび」があるかのように思い込むものである。
少なくとも、それは天意の生き方ではない。人為の生き方である。自分が自分で自分を振りまわしている状態である。それは人間本来の生き方とはいえない。
もちろんここで、「自然の法則」を説くつもりはない。本書では、法源誕生から17年目にして、ようやくつかめた天意を伝えるために、わたくし福永法源をさらけ出してみるつもりである。
さて、少々結論めいたことをいうならば、私たちの生とは山水画の白い部分にあるといえる。文学ならば行間に生があるといってよいだろう。そこがキラキラと輝いてこそ、花が咲くのである。
なにも見えないと思えるところ、なにも聞こえないと感じるところ、なにも触れていないと思えるところ、なにも意味がないととらえているところ、なにも役に立たないと思いこんでいるところ、なにも育たないと思えるところ……、要するに、私たち人間の最高の華は、人為ではとらえきれないところで素晴らしく咲くのである。いわば、天意のみによって、見事な人生の花が咲くといえるのだ。