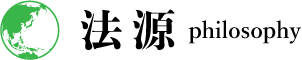第一章 天意
【5】
毎朝毎晩「天声」を聞く身となった私は、その理解度はともかくとして、自分のなかで具体的な変化、現象が起こり始めていることに気づいていた。
その第一は「
いまでは「
たしかに、「不思議な力、とんでもないものが備わってしまった」という実感は強くあった。しかし、その実感が強ければ強いほどに、なかば恐れに似た恐怖感をいだいたことをよく覚えている。
とにかく、自分でもにわかには信じられないほどの〝超・能力〟なのである。たとえていうならば千里眼とでもいおうか。私の周囲の人の状況が、まるで映画を観ているように脳裏に展開するのである。
たとえば、私のところを訪ねて来る友人がいたとしよう。すると、彼がいまどこにいて何をしているのかが逐一わかってしまうのである。
「あっ、いま電車を降りた。階段を上った。歩道を渡った……。もうすぐドアのところに来るぞ」
と、ちょうどそのとき、私の部屋のドアをノックする音が聞こえてくる。やっぱり、見えたとおり、そのままなのである。
そのようなことがいつ何時でも脳裏をかすめるものだから、ますます自分の能力に恐れることになる。しかし、その反面、「これはすごい力を授かったものだ」と、内心穏やかではない自分がいた。
問題は、この「
早い話が、もてあましていたのである。だいたい超能力などというものは、物語では3回使うと終わりなどという制限がついているものであるが、私の授かった「
そんなある日のこと。私は、友人の一人であるK君と話をしているときに、ふっと悪戯心がめばえ、彼を驚かせようと、唐突にこう切りだした。
「これから君の昨日一日の行動を当ててみようか」
言われたK君は、きょとんとしている。まるで私の言ったことが理解できないといったふうである。私は再度、同じことを伝えた。
「ほおう」
やっと理解したK君は、半分あきれ顔である。やれるならばやってみろと言いたげであった。私は調子にのって、彼の昨日の朝から夜までの一日の行動をこと細かく話し始めた。
「君は、朝6時××分に起きると、顔を洗って、歯を磨いて、それから朝食は××と××を食べ、食事を終えるとトイレに行って、それから……」
「ふん、ふん」
最初はおもしろそうに聞いていたK君だったが、話が昼ごろのことになると、だんだん真顔になってくるのがわかった。しだいに顔が青ざめてくる。私がさらに詳細に伝えると、突然、
「もうわかった、わかったからやめてくれ。もう十分だ!」
そう大声で怒鳴ったのである。K君は、まるで私を化け物でも見るような目つきでにらんでいる。それは絶交の態度でもあった。
それ以来、K君とは会っていない。この不思議な力を使う私を気味悪がって去っていった友人はK君以外にも何人かいた。まだまだ、天声というものの実体がよくわかっていなかったころの話である。
しかし、少しずつではあるが、私の周囲には、「天声」が人知を超えたメッセージであることを気づいてくれる人が多くなっていた。「天声」で伝えられた内容を告げると、姿勢を正して耳を傾けてくれるようになり、それにともなって次第に知人たちの様子も変化をみせていた。
そのころである。私は「天声」の正体をかいま見ることになった。
じつは、とんでもないことが起こったのである。私は相手の気持ちや行動が逐一読みとれることをいいことに、得意がって友人にいろいろとアドバイスしていた。ところが、そのときは必ず失敗することがわかっていながら、その友人は決行するといって聞かないのである。彼の性格からして、決めたことはやるに決まっている。そこで、どうしても止めたい一心で、こう言ってしまったのだ。
「これは、天声だぞ」
その瞬間である。野球のバットのようなもので、後頭部をおもいっきり殴られたような衝撃を受けたかとおもうと、私はそのまま気を失ってしまった。
後で聞いてみると、私は3時間も意識を失っていたらしい。そして正気になった瞬間、激しい天声が身体を流れていった。
「天声とは、おまえの言葉ではない!」
それは驚きである以上に、自分の位置関係がはっきりと明確になった瞬間でもある。私は「天声」を再現する道具なのである。そのまま伝えるパイプ役なのである。そのことが理解できたのだった。
ただし、私には大いなる疑問がわいた。
「なぜこのような力を授かったのだろう。そして、これからどういう人生を歩むのだろうか」と。
だが、いくら自問自答しても、答えはわからなかった。はっきりしていることは、もう人並みの人生は歩めないということである。そのことだけが漠とした不安としてつきまとっていた。
「もういやだ、普通の人間に戻りたい」
私の葛藤はしばらく続いた。知らなくてもいいような相手の気持ちが読めてしまう。人間の
生身の私には、この状況は耐えられないのではないかと、何度も思ったものである。そして同時に、「天声」のすごさも目の当たりにするようになっていた。