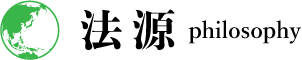第二章 是空
【8】
15分もたったころだろうか。私の耳に、ひとつの言葉が響いた。
「私が貸してあげよう」
たしかにそう聞こえた。驚いて顔を上げると、そこには怖そうな顔をしたおばあさんが立っていた。質屋の親父の後ろに、そのおばあさんの姿が重なっている。親父は振り向くなり、そのおばあさんにこう言った。
「おばあちゃん、ここは質屋だよ。質屋が人情に負けてちゃ商売にならないよ。いいから奥に引っこんでいてください」
「いや、商売は関係ありません。私がこの人を信用して、自分のお金を貸すのだからよろしいでしょ」
おばあさんも負けてはいない。私の目の前に30万円の札束を差し出して、息子の意見をまっ向から押しかえした。これを地獄に仏というのだろうか。その
私は、目の前に置かれた30万円を受けとると、
「銀行に入れてきたら、私はここでなんでもします。何日間でもご奉公させていただきます。とにかくこのお金をお借りいたします」
と伝え、会社の住所と電話番号をメモしておばあさんに渡した。
あとは一目散である。質屋を飛びだし、銀行めざして走った。おそらく、ものすごい形相だったに違いない。すれちがう人があわてて飛びのくほどの勢いであった。
銀行にたどり着いたときには、時計の針が3時30分を指していた。銀行のシャッターは降りている。万事休すである。へなへなと腰くだけになって、私は道路へしゃがみ込んでしまった。
そのときだった。銀行の脇に扉らしきものがあるのを発見した。気力を振りしぼって近づいてみると、そこには「通用門」と書かれていた。おそるおそるだが、そのドアのノブをまわしてみると、鍵はかかっていない。手前にドアをひくと、なんと扉が開いたではないか。中に入ると、まだ行員たちが忙しそうに働いていた。
「時間が過ぎてしまったのですけど、まだ入金できますか」
不安な心を押さえながら、私は質屋さんのおばあさんから借りた30万円を窓口に差し出した。係の女性は、ササッと機械を操作し、
「はい、これで入金はすみました。ご苦労さまでした」
と、まるで私の苦労を知らぬかのように、入金証を代わりに差し出してきた。
「これで大丈夫なんですね。ほんとうに大丈夫なんですね」
私は、三度念を押して聞いた。
「はい、もちろん大丈夫ですよ」
その言葉を聞いて、私は奇妙な安堵を感じた。奇妙というのは、達成したという安心感と、ほんとうに疲れたという疲労感が入りまじっていたからである。
さて、ふたたび通用門から銀行を出た私は、その足で先ほどの質屋へ急いで戻った。あのおばあさんは、カウンターのそばですわっていた。約束どおり、私の帰ってくるのを待っていてくれたのだと私は思った。
「ほんとうにありがとうございました。無事に終わりました。約束したように、今日からここで奉公させてください」
私は潔く頭を下げて申しこんだ。するとおばあさんは、
「ここで奉公しても、お金は返せないから、とにかく帰って自分の仕事をしなさい」
と、なかば私を諭すように言ったのである。
考えてみれば、おばあさんのほうに理があった。ここで奉公をしたとしても、給料をもらえるかどうかもわからない。ましてや質屋の経験のない私など、いないほうがマシなくらいである。それよりも自分のもっている仕事をきちんとやり、その利益のなかからお金を返したほうが早道である。結局、私はそのおばあさんの好意に甘えることにした。
それにしても、おばあさんの態度は、世間の常識をはるかに超えたものであった。これは一般の尺度では計れないものである。しかし、世の中には、このような大きな器をもった人がいるのだということがわかっただけでも、私にとってはプラスであった。
返済したのは、それから2か月後のことである。
このおばあさんとの体験は、その後の私を変えるに充分なインパクトがあった。まさに、お金では買えない貴重な体験をしたのである。