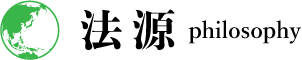「法源を引き出す修行が、法の華である」
これは、昭和55年1月6日の天声である。
「よろこびを売る事行」は、「法の華」と命名されていた。
私はことあるごとに全国を行脚し、天声開説会を頻繁に行っていた。その天声開説会にも、人が集まり始め、感動を超えた実証者が多数出てきていた。たとえば、マイクを通した私の声を聴くだけで、全身が熱くなったり、脚の悪い人が歩いて帰るようになったり、あるいは、お年寄りの腰痛がとれたり、腫瘍が消えたりといった、感謝のお便りもたくさん舞いこんできていた。
講演は、たいてい夕方か、休日であれば午後から始まった。当時は、飛行機で移動するなど考えてもみないことである。ほとんどは列車で移動し、その街のホームに降りたつことが多かった。
やがて、遠くの街からも講演依頼が届くほどになり、移動はいきおい夜行列車にならざるをえなかった。ネオン街がにぎやかになり始める時間に、私は東京駅から寝台列車に乗り、翌朝早くか午前中に地方の街に着いた。そして着くとすぐに、会場の準備をみずからでやった。
私の毎日は、夜と朝の天行力の時間を中心にまわっていた。どこにいても、地方の旅館に泊まっても、それだけは変わらなかった。
たとえば夜行列車の中でも、午前0時になると天行力を始めた。いまと違って当時の寝台ベッドはせまく、大きな身体の私には無理があった。横になるにも、上背のある私にはかなり窮屈で、脚を折り曲げなければならない。背筋などは伸ばしようのないほど、そんなせまい場所で、天行力を行っていたのである。
寝台では、なるべく声が周囲に漏れないように、毛布を頭からかぶって法唱をするほどである。それも、できるだけ小さな声で法唱をするように心がけていた。それでも、「うるさい、静かにしろ」と、見知らぬ客から怒鳴られることがしばしばだった。あるときなどは、下にいた客からいきなりカーテンを開けはなされ、かぶっていた毛布を強引にはぎ取られたこともある。
しかし、それはまだまだましなほうである。寝台が取れないこともしばしばあったからである。取れないときは、客車で移動する。あの座席は堅く、直角の背もたれであるから、尻の痛さで、何時間もすわっていられないこともたびたびだった。
そこで私は、天行力の時間になると、デッキに出ていった。薄ぐらい車内燈の下で、法唱し、天行力を送った。デッキにも人があふれているときなどは、トイレで行う。そんなときは、なさけない気持ちになったものである。
天行力を終えて座席に戻り、ぼんやりと通過する街の灯を眺めながら、「おれはいったいこの先、どうなるのだろう」と、自問することもあった。数々の実証があらわれているにもかかわらず、なぜか不安になるのである。列車の揺れと尻の痛さに一睡もすることができず、車窓からの暗い夜を眺めていた時代は、いまとなっては懐かしいが、まだまだ本気で〝大バカ〟に成れない自分のいたこともたしかである。