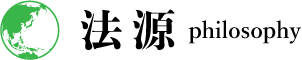第二章 是空
【7】
私は若さと体力にものをいわせて、それこそ不眠不休で働き続けた。そして、1年後には小さいながらも会社を興していた。手持ちのお金が3円しかなかった少し前のことを想うと、まったく夢のような現実である。
仕事の量に比例して、お金の動きも大きくふくらんでいく。やがて銀行口座を開き、大きな金額の支払いは約束手形で行うまでになった。銀行とのつきあいも順調にいき、まずまずの営業状態が続いていた。
ところが、会社を設立して2年目のこと、私が26歳のときである。
暑いさかりを迎えたある日、3時5分前ころに、銀行から一本の電話が入った。今日支払い期限の手形を落とすためには、不足のお金が生じている、という知らせである。くわしく聞いてみると、あと30万円ないと不渡りを出すことになるというのである。
「3時までにお金を用意して、窓口まで持ってきてください」
銀行の係員はそう告げると電話を切った。
〝不渡り〟
私はその言葉にあわてた。不渡りを出そうものなら、会社は倒産である。いままでの苦労は水の泡になってしまう。かといって、急場のことで手もとにそれだけのまとまった現金はない。しかも、あと5分で30万を貸してくれるようなところはない。ましてや、それほど裕福な友人もいない。
うっかりと手形の落ちる期限を忘れていた私がうかつであったのだが、いまさら後悔しても始まらない。なんとかしなければならない。どうすればいいのか。さあ、どうするか……。
私の頭は必死で回転するが、妙案など出てこない。しかたなく、取るものもとりあえず、私は銀行の支店がある武蔵小杉へ向かった。しかし、銀行へ着いたものの、中へは入れない。お金を持ってきていないのだから、銀行に入ったとしても意味がない。
私はおもわず、天をあおぐように顔を空に向けた。そのときだった。私の目に飛びこんできたものがあった。「質」と赤い字で書かれた看板が、私の目を射たのである。その看板だけが、なぜか浮きあがって見え、ひときわ大きくきれいに映っていたのだ。
次の瞬間、私はその質屋に走りこんでいた。中へ入ると、カウンターのむこうに、質屋の親父然とした中年の男性がすわっている。その男は、走りこんできた私をうさん臭そうな目で眺めまわしていた。それこそ、私を値踏みするような視線の走らせ方である。
「じつは、銀行から電話があって、手形を落とすのに30万円不足しているといわれたのです。お願いします。とにかく30万円貸してください」
なんと、私の口からは、普通では考えられないような言葉が出ていた。質屋でお金を借りる理由をいちいち言う人などいない。まず、質草を出してから交渉に入るのが普通である。
しかし、私はそのとき、なにも考えずに「30万円貸してください」と言っていた。いま想い出しても不思議だが、このときの私は、ドモっていなかったようである。なにかわからないが、自分のなかから言葉がすらすらと出てきたような気がする。しかし、この言葉を聞き終わるやいなや、
「質草は何があるのか」
と親父はたずねてきた。取るものもとりあえず会社を飛び出してきた私である。質草といわれても、着ている背広か安物の時計しかない。それはとても30万円の質草になるような代物ではない。
「なにもありません。なにもありませんが、30万円貸してください」
私にできることは、そう頼みこむことだけだった。そんな私を頭がおかしいやつとでも思ったのだろうか。
「ここをどこだと思ってるんだ。帰れ! 帰らないと警察を呼ぶぞ」
と親父が怒鳴った。その声を聞いた瞬間、私はカウンターの前で土下座していた。なぜだかわからないが、土間に頭をこすりつけていたのである。もちろん土下座をすればなんとかなるなどと計算したわけではない。自分でも知らないうちに、質屋の土間に頭をつけていたのである。
玄関の騒々しさに奥から奥さんが顔を出した。土下座をする私を発見して、
「あんた、この人、ちょっとおかしいから、早く警察に電話しなさいよ」
と、奥さんまでが罪人扱いである。しかし、そんな状況下にありながら、それでも私は「お願いします」を繰り返していた。