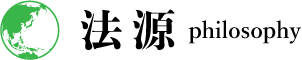第二章 是空
【5】
母は私の上京を快く承諾してくれた。出発の日、見送りはいらないという私の言葉を聞かずに、母は小郡駅まで来ていた。強がりをいって私を出した母であったが、駅構内に入るとすでに目に涙を溜めていた。
まがりなりにも母子二人で楽しく暮らしてきた生活が、この瞬間に途切れるのである。その身を切られるような寂しさは、出かける者よりも残された者のほうが大きい。私が夜行列車に乗りこむと、耐えきれなくなったのか、母は本泣きになっていた。
「い、いって、く、くるよ」
私は精いっぱいの言葉を母に送った。それがしばしの別れであった。
車中、私は十数年前に同じ列車で一人上京した母のことを想っていた。あのときは一人息子を置いての上京である。きっとつらい決断だったのであろうと思うと、いまさらにして悲しみが心を襲った。
東京での生活は、いろいろな意味で私を変えてくれた。まず、ドモリであろうとなかろうと、まったく他人のことは無関心という、大都会独特の解放感があった。私にとっては都合のよい環境といえた。
私は夜学の電気学科に通いながら、そのいっぽうでさまざまなアルバイトを体験した。ドモリという言葉の壁はあったが、都会人は許容範囲が広い。ドモリながらも会話に参加していくと、自然に仲間へ入りこめた。
バイトは、菓子職人の手伝いや、港湾での肉体労働など、やれるものはなんでもチャレンジした。
また、独り残した母を心配させまいと、私は毎月定期的に手紙を出した。母からの返事は、学生運動を心配する内容が多かった。このころちょうど、70年安保の嵐が吹き荒れていたときで、新聞やテレビなどで連日、大騒ぎをしていたからだ。しかし、夜学生はこれといった行動を起こすこともなかった。
この時期、もっとも鮮烈な想い出は、恋愛だろうか。
どこでどう知りあったのかは定かではないが、つきあい始めてからのことはよく覚えている。どちらも一目ぼれであった。黒髪の長い、目のクリッとした女性である。私にとって女性を好きになったのは、これがはじめての体験である。
昔、同居した年上の女の子に、淡い恋心を感じたことはあるが、それは恋愛対象とはいえなかった。なぜならば、亡くした姉の面影が重なっていたからである。どちらかといえば、姉弟になりたいという気持ちのほうが強かったかもしれない。
本気で女性を好きになったのは、やはりこのときである。お互いに好きあっていた。しかし、長くは続かなかった。
二人を引き離そうとする目に見えない大きな壁が立ちはだかった。どうにもならない現実が複雑にからみ合い、二人の仲はひき裂かれていった。
だが、私はあきらめきれなかった。もう一度会えば状況は変わるかもしれない、そう思い、必死で彼女のアパートまで走り、ドアを叩いた。だがドアは閉ざされたままだった。私にも彼女にも、もう二度と二人が会えないことは十分承知していた。ドアを開けようにも開けることのできない彼女の気持ちは痛いほどわかっていた。
私は夜明けまでアパートの前で泣きあかした。どうすることもできない自分の不幸を嘆いた。私は失意のどん底に陥り、すべての判断力が停止してしまっていた。
いま、私のもとに若い方が恋愛問題に悩んで相談に来られる。もちろん答えは、天声で示されるが、そうでなくても生身の人間である私自身も、その恋の行方は見える。だめなものはなにをやってもだめであるし、縁があれば嫌でも結ばれる。お互いに好きだからという愛情だけでは絶対に解けない「赤い糸」の結びつきが存在するのである。
恋愛は、相手があるだけに、自分の都合はいっさい通用しない。ましてや恋愛後に結婚、出産という人生の大事業が待っているとなれば、「縁」の大切さが認識できるはずである。いわば個人的な恋愛とはいえ、それは未来につながる重要な事業でもあるのだ。
さて、死んでいたかもしれない重大な事故を経験したのも、この時期である。それは大学で柔道の練習をやっているときに起こった。背負い投げしようとした私の背中を、切り返そうとした相手の膝が強打したのである。その事故で、私の腎臓の1つが破裂し、生死の境をさまようことになった。
私の身体は強じんにできていて、風邪ひとつひくこともなかったので、入院というのははじめての経験である。ただし、私は病院に担ぎこまれたことも、緊急手術を受けたことも知らない。昏睡状態のままであったという。気がついたときには、病院のベッドでウンウン
昏睡から醒めてまず思ったのは、幼いころ私のために、必死にお百度を踏んでくれた祖母の顔であった。ベッドの上で、私はあらためて祖母のありがたみを感じていた。不思議な体験でもあった。
その後、私は大手電気メーカーでも働いた。臨時の身であったが、身長が高かったので目立ったのだろう、労働運動に引っぱりだされたことがある。とくに何をしたというわけではない。デモのときに、いちばん前列で大きな声を張りあげていただけである。
調子者というわけでもないのだろうが、大声や身長をほめられただけで、私は得意になってデモの最前列に向かってしまう質らしい。そうした親分肌のあることも否定はしない。だからといって得をした経験はまったくない。