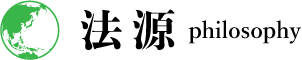第五章 法源
【3】
私の吐く「天声」は、言葉ではなく、〝波動〟である。
そのために、「天声」をナマで受けとると、そのパワーによって
しかし、それはそれである。少しくらいの効力があるからといって、それを売り物にするのは「天意」に反することである。少なくとも私は、「よろこびを売る
ましてや、波動パワーを売り物にして、痛みや悩みを手軽に取りのぞいてしまったならば、本来の使命から外れてしまうことにもなる。頼む・すがる・求めるといういちばん排除しなければならないことが、逆に増長される結果につながることにもなるからである。
また、一時的に痛みは取れたとしても、その人の痛みを発生させている問題の根は、なにひとつとして解決されないわけであり、この部分においても、「天意」に大きく外れる行為とわかったのである。
問題をかかえすぎ、せっぱ詰まった状態の人の場合はともかくとして、むやみに
いわば、問題も病気も他人が解決してはならないのである。その本人が引きおこした問題、病気であるからには、その本人が自分の生きざまの過ちに気づき、目覚めて解決しなければならないのである。
このように説明すると、一見、ひどく残酷なように聞こえるかもしれないが、これが真理なのである。
ましてや、大切なことは、そうした自分で引きおこした問題は、必ず自分の力で解決できるという真理も、その裏側にはあるということである。他に頼み・すがり・求めなくても、自分のなかに解決の力は備わっているのである。
たしかに、自然の法則のなすことには、いっさいの同情も甘えも通用しない。しかし、そのために、「行」が私たちにプレゼントされているのである。それは、
「自分の力で解決しなさいよ」
という「天」からの貴重な贈り物である。もしも問題や病気で行きづまったとしても、そこには自力で解決できる「行」という素晴らしいものが用意されている。決してあきらめることなく、最高のよろこびのままの人生を送りなさいよと「天」はいっているのである。
そもそも私たち人間は、天によって生かされている。この事実にまず気づくべきであろう。そして次の「天声」を感じとってほしい。
「目に見えないものを見よ。
耳に聞けないものを聞け。
成るべくして成れる、人間本来の力、法源を感知せよ」
恐ろしく力強い「天」の波動によって、私の身体をつらぬいていった言葉である。そこには人間本来の姿が伝えられていた。それは法を
私たち人間は、いま生かされている以上、精いっぱい、法則に沿って生きることなのである。誤解を恐れることなく、一瞬一瞬をよろこんで、答えを気にせずに、人々をよろこばせ続けて生きることなのである。
これが本来の人間の姿であり、ほんとうの人生なのである。
ここにいう「法」とは、「あたりまえ」の道である。決して特別のものではない。あたりまえに生きることが大切なのである。しかし、このあたりまえに生きることができないために、私たち人間はいまここに生かされているといってもよい。「天声」に、
「人間は不完全であるから生きているのである」
というものがある。私たちは完全な人間ではない。不完全だからこそ生きていることの意味というものがある。その事実に目覚めたならば、いまなにをなすべきかがわかってくるだろう。……本物の人間になることなのである。
さて、昭和60年に、私ははじめて「
「天意」はあくまでも〝実証〟されて〝真理〟である。その〝実証〟する力が私についてくるのを見はからいながら、「天」が次々と「天声」で伝えてくるとなれば、それに応えていくしかない。「法の華」においては、立ち止まることは絶対に許されないことなのである。
その修行は、伊豆大島で行われた。2泊3日だった。
全国から大勢の方が、その「法源誕生5周年特別特訓」に参加された。
東京の竹芝桟橋から船で大島に渡るのだが、修行はすでに船内において始まっていた。外海の大波にもまれながら、私の法話が続く。参加したみなさんの顔は、すでに期待でいっぱいの様子であった。
大島に船が着くと、その期待感はさらにふくらんで、爆発寸前の状態である。そして島に降り立った瞬間、ついに
私たち一行は、薄く霧が立ちこめる三原山へ全員で登った。Tシャツでは少し肌寒かったが、気にはならない。身体の芯から熱く燃えていたからである。山頂へたどり着いてから、しばらくして、一人ひとりが大きな
だれもが、大自然の懐に放たれたように、自由に動いて、動きまわった。三原山とくらべたならば、そこにうごめく人間の姿はちっぽけなものである。しかし、
修行生のなかには、初日から
はじめての「
「
まったく「天声」の示すとおりの答えがあらわれていた。そして、
そのときである。不思議なことが起こった。
なんと三原山が噴火したのだ。
ズーンという重い地鳴りとともに、地は震動し、溶岩が噴き出した。その溶岩は
「三原山が、『
と、どよめきと感動の声があがった。
初の「
これには後日談がある。
噴火はしばらく続いていた。東京へ戻ってからも、テレビ、ニュースなどで、刻々と変わる火山の様子が中継されていた。噴火が静まるころになると、溶岩も冷えて流れを止めつつあった。そのとき、おもわずテレビ画面に引き寄せられた。
なんと町のむこう、修行生が歩いたその道で溶岩が止まっていたのである。