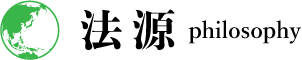第七章 超宗
【4】
この世の中は、自分の力ではどうにもならない。
このことを、はっきりと自覚することが、まず第一であろう。
いくら自己改造をやったとしても、それが人為(人間の発想の範ちゅう)のなかで生まれたものであれば、絶対に自分などは変わらない。もちろん理論理屈がいくら立派なものだからといって、それで変われるわけがないのである。
理屈に合わない、常識と違うといったところで、それは私たち人間のレベルの判断基準でしかない。そのような基準に振りまわされるよりは、「天にゆだねて、生かされていることのいまをよろこべる自分に成る」ことなのである。
それが損か得かなどという計算はいらない。
自分の力でどうにもならないのであれば、「天にすべてをゆだねて」素直に生かされればよいのである。それだけのことなのである。自分で、自分が、という自分中心に生きている傲慢さが、人生のなかでさまざまな問題を引き寄せるのである。
損か得かという計算はいらない、というのは、次の「天声」にヒントがある。
「蓮はドブのなかに身を沈めてはじめて美しい花を咲かせる。しかし、花を咲かせることだけが人生ではなく、ドブになることも人生である。そして、周囲に美しい花を咲かせなさい」
みなさんだれしもが「花」になりたがる。しかし、ドブもまた「華」なのである。
私が「天意」のままに〝大バカ〟をやっているのは、この「天声」のままに生きているからである。一部の無理解な方の問題が波及して、それがマスコミで騒がれ、誤解のうえに誤解をまねき、社会人として屈辱的な汚名を甘んじて受けているのも、美しい花をこの地上に咲かせんがためなのである。
もちろんこれは正義感ではない。正義を振りかざすならば、マスコミを相手に戦っていることであろう。そうではない。無抵抗でいいのだ。理解していただくまで、じっと待てばいいのである。
自分という枠を超えて、「天意」のままに、「天声」の指示するままに、最高の
さて私自身、この世の中は自分の力ではどうにもならないということを、まざまざと見せつけられたことがある。それは必要なときに「天声」が過去に2回、出なくなったことである。それは、京都と鹿児島の講演会であった。
その日の講演には、大勢の方々が詰めかけ、会場には熱気さえあった。行者のみなさんは、ひさしぶりの地元での講演会に、いまや遅しと身を乗りだすように待っていてくださった。私自身も控室で張りきって時間を待っていた。
ところがである。演壇に立ってマイクを握っても、天声が出てこないのである。いつもならば、自分でも驚くくらいにスラスラと言葉が流れるように出てくるのに、この日にかぎって、まったく「天声」が出てくれない。それこそ、身を絞ってもひと言の「天声」も出ないという状態である。
私は、会場いっぱいの人々を前にして、ただただマイクを握っているだけである。「早く講演を始めなければ……。大勢の方々に天声をお伝えしなければ……」と、演壇の上であせり始めていた。
事前に「今日は講演会を開いてはいけない」といった「天声」でも出ていたならば動揺もしないが、そうではない。突然なのである。
私はとにかくなんとかしなければと、マイクを握りなおしてみたり、大きく深呼吸をしてみたりと、必死の思いで「天声」の出てくるのを待った。しかし、それでもなにひとつとして出てこない。
ここは自分の記憶している「天声」をならべるしかないだろうと、頭の中であれこれ考え、それではとマイクに向かってしゃべろうとしたが、どうも自分でしゃべろうとすると、ドモッてしまって、ひと言も言葉が出ないのである。
なぜに「天声」が止まってしまったのか、いまでもよくわからないが、その答えは、次にとった私の行動に意味があるのかもしれない。
私は「天声」を伝えるのをやめて、控室に戻り、これまで自分が記してきた「天声ノート」を持ちだして、あらためて壇上へのぼったのである。私は「天声」の出ないことをおことわりして、この「天声ノート」を講演会場ではじめてお披露目したのである。
これならば頭で考えなくても、「天声」を正確に伝えられると思ったからである。そしてそのとおりになった。会場のみなさんは、その言葉から伝わってくる波動を、そのまま受けとってくれたのである。
たしかに、「天声」がじかに伝わらないという不備はあったが、それでも「天声」の言葉が、人の