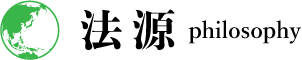第一章 天意
【4】
そんな母子に、「天声」は無情にも厳しい言葉を平気で投げつけてくる。
なんと……、母と縁切りをせよというのである。
そのころの私は、死の幻想から醒め、たくましく生きようと、新たな熱意で事態の収拾に走りまわっていたところであった。たしかに、毎日、ふり注ぐように「天声」は私の身体に流れこんでいたが、当の私は、それにしたがうどころか、それを理解しようという努力にも乏しかったのである。
正直なところ、当初は、「天声」のことを他人に話しでもしたなら、「頭がおかしくなったのではないか」などと茶化されるのではと、そればかりが気になっていたのである。あるいは、もしも安易に打ちあけて、友人から「霊がついた」などと、騒がれ
とにかく、正直なところ「天声」は、当時の私にとっては、非常に重荷だったといっていいだろう。そのころの私の立場になって少し想像してもらえば、その微妙な気持ちがわかると思う。
ある日突然に、自分のなかに「天声」が流れてきたならば、いったいどのように対処するだろうか。だれもがあわてふためき、「なにごとが起こったのか」と、激しい心の葛藤を起こすに違いない。
しかし、そんな私でも、時間になるとノートとペンを用意して、毎朝毎晩「天声」を書きとっていた。もちろん内容は、半分もわかっていない。わかってはいないが、いずれわかるときが来るだろうと、そんな気持ちでノートをとっていたのである。
そしてある日、「天声」は、突如、母との縁切りを示したのだ。
子育ての厳しさは現代も変わりはない。いくら親類に助けられていたとしても、女手ひとつで子どもを育てるのは言語を絶する厳しさがある。そのことをよく知っていた私は、独立して事業を軌道に乗せると、すぐに母を故郷から迎えたのである。
それは、母への強い情愛と感謝といった、月並みの言葉で言いあらわせるほどの理由だけではなかった。前述したように、法源誕生と十万巻の写経が同時進行したほどに、他の親子以上に強く太い親子の絆からである。
しかし「天声」は、そんな私たち親子の絆を断ち切るかのごとくに、母を旧性に戻すように伝え、さらに、今後は日常会話や生活に至るまで、他人として振る舞うよう求めてきたのであった。
これにはさすがに私自身、「やっぱり悪霊だったのか」と「天声」を疑ってみたものである。しかし、「天声」である。信じる信じないは別にして、いちおう、そのような「天声」のあったことを私は素直に母へ伝えた。
すると、どうであろうか。それを聞いた母は、ひとことも告げることなく、まさに素直に「天声」にしたがい、すべての手続きをみずから進んでやってしまったのである。このときの私のショックは、小さくはなかった。
母は、私を通じてしか「天声」を聞くことができないが、その「天声」を聞ける本人よりも純粋に、素直に受けとることができたといってよいだろう。その日から、母は私の母ではなくなった。
いや、私が母の子どもではなくなったのかもしれない。
いつまでも〝福永輝義〟を引きずって、福永法源としての自覚にとぼしい私を、天は厳しく戒めたのであろうか。ひどい仕打ちとはいえ、ここまで徹しないと、「天声」を伝えるパイプ役にはなれなかったのだろう。
いまとなってみれば、母からの訣別を意味した厳しい「天声」は、素晴らしい愛に満ちた言葉であったと理解することができるのである。
『天声聖書』をひもとくと、初期の「天声」がずらりとならんでいる。ストレートに理解できるものもあれば、実に難解なものも一緒にならんでいる。当時の私は、多少の宗教的知識を有していたが、34年少々の人生ですべてが解けるものではなかった。ましてや、過去に受けた教えの無力さを、自殺寸前という形でまざまざと見せつけられた後とあっては、信じられる宗教的知識などはないに等しかった。