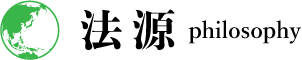第二章 是空
【1】
私たち人間の成長過程において、幼児期の体験は大きな影響を与えるといわれている。しかし、その大切といわれる幼児期の環境は、残念なことに私たちの勝手で選べるわけではない。
親を選べないのと同様に、環境もまた親が築いたものだからである。
ましてや、どのような家に生まれ落ちるのかさえまったくわからぬまま、突如としてこの世に生を受けているのが現状である。
「どうせなら、もっと裕福な家に生まれればなあ」
「優しい両親のいる家がよかった」
そんな会話を交わした人は多いはずである。しかし、実際には、自分ではなにひとつとして選ぶことのできない現実が横たわっている。なぜ、この家に生まれなければならなかったのか……。そんな疑問さえわいてくる。
たしかに生まれ落ちる環境は一人ひとり違っている。百人百様の違いがある。だが、はっきりいえることは、その環境は、その人が人生をこれから歩む過程において、必要だから与えられたものである。人知をはるかに超えた「自然の法則」そのもので決定づけられるものが、生まれてくる家の環境なのである。
したがって、一見、不平等に見えてしまうことも、自然の法則からすればすべて平等なのである。その人、その家族に必要だからこそその環境が与えられているだけで、たとえ家が貧しくとも、片親であっても、そこからスタートをきらなければならない目に見えない理由が存在するのである。
だから、それを「問題」として「握りしめてしまう」「自分」に問題があるといってよい。要するに、貧乏も片親も、本来は「問題」ではないのだ。それを問題として考え、とらえて苦悩してしまう本人に問題があるといえるのである。
その本人が「問題」を問題として受けとめなければ、だれでも人間としての平等をもっているのである。しかし、いずれにせよ、この事実を幼年期にみずから発見することなどは、私たちの知識では無理な話である。
この私もまた、生まれた環境下で苦悩の人生を体験することになったのである。
幼いころの私は、ドモリどころか声さえ出せない最悪の状況に置かれていた。
終戦の混乱のなか、母は自活の道を求めて東京の洋裁学校へ入り、残された私は、5歳のときに母の実家に預けられた。せめて味方として姉が生きていれば心強かったのだろうが、その姉は少し前に死去していた。そんな孤独な状況下にあったためか、私はますます無口になっていたようである。
山口県・阿知須の夏は暑かった。
母の実家で一人残され、寂しい思いをしている孫を
「お父さんがいなくても、父さんのぶんまで強くなって生きんと、父さんがっかりするけんね」
と口癖のように言っていた。
祖母は優しい人であった。いま想えば母の優しさは、祖母の影響かもしれない。祖母は私にいつも父親のことを話してくれた。それが私のお気に入りの話であったからなのであろう。私は父親の話になると、目を輝かせて聞きいっていたらしい。
しかし、ドモリで無口な私は、祖母の話に相づちの一つも打てなかった。
口癖といえば、小学校の元教員の伯母も同様に、
「輝ちゃん、強いよね」
が口癖である。
伯母の2人の息子も、そう言って私を励ましてくれていた。私にはその愛情が痛いほど伝わってきた。それゆえ、そう励まされれば励まされるほど、自分の置かれている環境とのギャップで、心の葛藤が増すばかりであった。
伯母の家には、同じ年代の子どもたちがいた。間に長女をはさんで、年上と年下の従兄弟がいるわけだが、いま想えば、突然に伯母の家へ上がりこんできた私は、異邦人に映ったに違いない。かっこうの遊び相手であった。
阿知須は、私の生まれ育った宇部市内とはだいぶ
その自然の環境のなかで、私たちはよく遊んだ。阿知須には木陰もたくさんあった。蝉の鳴き声がやかましく、とんぼも数えきれないほどうじゃうじゃいた。なぜか、夏のことばかり覚えている。きっと楽しかったのだろう。
従兄弟たちは騒ぐように遊んだ。ナマズもとれたらもう大騒ぎである。私はそんな彼らに黙ってついていくだけである。非常に暗い子どもだったと思われていたであろう。
遊びのさなかに列車が通ると、私はいつも動きを止めて、ふり向いて見ていた。もちろん列車が珍しいわけではない。母と姉が恋しかったのである。
列車は私の大好きな人を運んできてくれる唯一の助っ人であった。希望をかなえてくれる頼もしい存在なのである。それは死んだ姉まで運んできてくれそうな、そんな期待までいだかせてくれた。
旧家らしい落ちついたたたずまいの家には、母の両親と、伯父の家族が住んでいた。大家族だけに夕食どきはにぎやかであった。
「ごはん、もっと食べなさいよ」
伯母が言う。戦後まもなくのことだけに、世の中は食料難の時代であったが、そこは田舎である。食料自給ができたので、困ることはなかった。
「おかわり、おかわり」
食べざかりの従兄弟たちは競っておかわりを要求した。
「輝ちゃんは?」
黙っている私に、伯母が聞く。
「……」
私はそうっと茶碗を差し出す。じつは、もっと前から私の茶碗は空になっていて、残った漬け物を相手に箸だけが動いていたのである。どうしても「おかわり」が言えないのである。これは子どもの遠慮ではない。ほんとうに言葉が出なかったのだ。
「ちゃんと自分で言いなさい」
伯父が厳しい口調で言う。
「……」
それでも私は黙ってもぐもぐ食べるだけである。やはり言葉が出ない。わかっていてもそれが表現できないことのつらさは、並大抵のものではない。祖母が心配そうに目線を向けてくる。私は下を向くしかなかった。
独りぼっちの預かりっ子だったが、不満は何もなかった。ただ、自分の名前さえスラスラ言えない自分が恥ずかしかったくらいである。もちろん母のいない寂しさはあったが、それは優しい祖母が補ってくれていた。
祖母は私を自分の子どものように慈しんでくれた。私のドモリを心配して、お寺参りをしてくれるほどであった。その祖母も1年後に他界してしまった。当時は、相当にショックを受けたのだろうが、現在の記憶では、祖母の死よりも生前の優しかった想い出のほうが多い。
その祖母のおかげで、小学校へあがる前には、強いドモリながらもなんとかしゃべれるようになっていた。