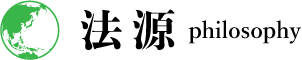第二章 是空
【3】
そんな私だったが、小学校5年になると、みずから進んで「生長の家」に通い始めた。もちろん、学校から帰ったら、母も日課のお参りが待っている。そのために朝だけ、6時からの約1時間、「神想観」に参加した。
それは、365日。丸一年続けて、ピタリとやめた。始めたときもやめたときも、これといった理由はない。しいていうならば、当時は宗教ブームであったことだ。とくに日蓮宗系の創価学会の台頭がめざましく、小中学生の間でも参加する人が多かった。
さて、肝心のドモリはといえば、なんの進展もみられなかった。宗教の教義を勉強したからといって、それで問題が解決するわけでもない。中学に上がっても同じような状態であった。いや、思春期に入ってからは、よけいな不甲斐なさを意識させられ、ますます自分が嫌になっていった。
とくに国語の時間は苦手であった。たとえばこうでぁる。
「今日は、何日か」
国語の教師が生徒に
「27日です」
と全員が答える。すると、
「よし、27番、教科書を読め」
という具合に、私の番がまわってくる。そう言われたときから、背中には汗が伝い始めている。最初の文字は、ひらがなであったが、
「……う、う、う……」
と声にならない。身体をよじって、音を出そうとするが出ない。わかっているのに、その声が出ないのであるから、自分でもいら立ってくる。
「おまえ、中学にもなって、まだ本が読めんのか」
「……」
これほどの誤解はない。読めないわけではないのである。発声ができないだけなのだ。級友たちはクスクス笑っている。
「まあいい、すわれ」
屈辱的な瞬間である。ホッとする気持ちよりも、くやしさで胸がいっぱいになった。うつむいたままじっとしていると、自分がますます人から離れていくような気がした。くやしさと、なさけなさでその場から走りだしたいほどであった。
国語のない日はホッとした。しかし、体育の時間はまた悩みであった。
中学の体育には、点呼がある。教師の笛を合図に、「走れ」「整列」といった順に校庭でならぶわけであるが、その教師は、身長の高い順番にならばせた。私は、2番目に背が高かった。
「よし、番号っ」
体育教師の号令がかかる。
「イチッ」
「……」
2は私であるが、やはり声が出ない。
「コラッ、なにやっとるか。もう一回。番号っ」
「イチッ」
「……。」
何度やっても結果は同じである。今度こそと額にしわを寄せて、なんとか発声しようとすると、意識が先走りをしてしまうのか、1番の者と同時に声が出てしまうこともある。
「ふざけるな」
教師が血相を変えて飛んでくる。そしていきなり私の襟首をつかむと、往復ビンタを張った。いまでは暴力教師のレッテルを貼られてしまうが、このころは往復ビンタなどは日常茶飯時である。
それでも、学校には楽しいことがたくさんあった。とくに柔道部は楽しかった。身体を動かし流れ出る汗は快感でもある。私は畳の上で、自分を精いっぱい解き放った。
その楽しみも卒業がせまってくるころに、新たな悩みで押しつぶされていった。