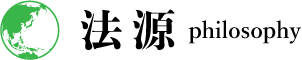第二章 是空
【6】
人生の転機といえるのは、22歳のときであろうか。
このとき、なぜか知らないが、無性に内から駆りたてられるものがあって、私はおもいきって独立したのである。その理由を探そうと思うのだが、うまく理由として成りたたない。わかっていることは、「このままではいけない」という気持ちである。
だからといって、なにが「このままではいけない」のかという、その理由はさっぱりわからない。逆にいえば、理由がありすぎたのかもしれない。いずれにせよ、そんな気持ちに突き動かされて、私は独り立ちをした。
ただし、要領が悪いというか、計画性がないというか、勤め先から飛び出したときは、給料日の3日前であった。勝手に辞めてしまったこともあって、給料をもらいづらくなってしまったし、ボーナスの支給対象にもならず、ましてや退職金など出るわけもなかった。
ポケットに残っていたお金は、わずか120円である。私はそのお金で、コーラのロングを買い、28円の銭湯に入った。流し場でごしごし身体を洗っていると、なぜか口から「えいっ」と元気なかけ声が湧いてくる。
おもいきって辞めたことで、けっこう気分がそう快なのかもしれなかった。風呂屋は早い時間だったので客もまばら。大きな風呂桶をひとり占めしていると、気分がさらに大きくなるようであった。
とにかく、さっぱりした気分だった。これからは、思う存分自分のやりたいことができると思うと、わくわくした
さて、残金は13円。私はその10円で、お世話になった先輩に電話した。
「どうやって食っていくのか、あてがあるのか」
電話口で心配する声がする。
「あ、あ、あてなどありません」
「仕事するのか」
「まだ、なにも決めていません」
そんな短いやりとりが何度か続いた。そのうちに、独立したならと、その先輩からトレースの外注仕事を頂いた。これが独立して第一号の仕事であった。
それにしても先輩が電話で指摘していたとおり、私の独立は無謀のようである。なぜならば、やりたいことも決まっていない状態であったからだ。それだけに、先輩からの仕事はありがたかった。もしも、あの電話をかけなかったならば、いったいどうなっていたことか。しかし、その反面、ちゃんと仕事を手にしたではないかという有頂天な自分のいたこともたしかであった。
トレースの納期は、1か月先である。私はさっそく、せまいアパートの一室で仕事にとりかかった。しかし、現実問題として手元には3円しかない。いくら元気者だからといって3円で1か月は暮らせない。
なにか買い置きはなかったかと台所を探ってみると、以前買い求めてあったインスタントラーメンが一袋だけ残っていた。
「よしっ、ついてるぞ」
なにもないと思っていただけに、一袋のラーメンが宝物のように輝いて見える。このときは、独立できた喜びのほうが、先の不安よりも勝っていたといえるだろう。しかし、現実は厳しい。その目先の喜びは、空腹の辛さにだんだん負けていった。
空腹になると、ラーメンの袋を開け、かたまりの端っこを少し割って、口に含んだ。パリッとした音がして、麵が口の中でくずれる。それを舌の上に乗せ、じわっと広がる麵の味を腹いっぱいに吸収する。それからゆっくりと水を飲んで、口の中で麵がふやけるのを待った。
もちろん、これでお腹がいっぱいになるはずがない。しかし、他に手だてはなかった。毎日、腹が空くとラーメンのかけらをかじりながら、なんとか二十数日間、自分の腹をだましてきた。最後の数日は、それこそ袋の底のカスのような麵を水と一緒に飲みこむだけで我慢したほどである。
このような飢えとの戦いは、若かったからできたのであろう。さらには、徹夜に近い毎日で、期限前に仕事を仕上げたのであるから、自分でいうのもなんであるが、その根性たるやただ者ではあるまい。
あとは、一分一秒でも早く納品して集金することだけである。そして腹いっぱい飯を食うことであった。
その夜、指定請求書に仕事内容と金額を書きこんだ。生まれてはじめて請求書というものを書いたが、そこには、会社員時代には味わうことのできなかった満足感があった。自分一人で仕事を仕上げて納品する。その努力の報酬として、お金がもらえるわけである。なにか自分で人生を切り開いているかのような、そんな大人っぽい感覚があった。独立の第一歩としては、悪くはなかった。
電車賃もないありさまだったので、先方の会社までは歩いて行った。1時間以上歩くことになったが、ポケットにしまった請求書に手をあてると、そんな苦労は簡単に吹き飛んでしまった。不思議と自分がリッチな気がするのである。
しかし、世の中はそう甘くはなかった。無事に納品を終え、言われたとおりに請求書を出しに行くと、信じられないような言葉が聞こえた。私は一瞬、自分の耳を疑ったくらいである。
「請求書は経理にまわしておきますから、1か月後に取りに来てください」
担当の声はあくまでも事務的である。あたりまえなのだろうが、まったく悪気を感じていない。私の脚から力が抜けていくのがわかる。気抜けとでもいうのだろうか。しかし、これ以上の空腹はまっぴらである。私は恥も外聞もなく、おもいきって聞きただした。
「す、すぐにお金がほしいのですが」
しかし、そんな個人的な事情が通用するはずもない。答えは同じであった。私はまったくそういう通例に
さて、納品はすんだが、現実にお金が手に入るのは1か月先のこと。今度の1か月は一袋のラーメンもない。あるとすれば、親にもらったこの肉体だけである。帰り道、私は肉体労働をやる決心をした。
決まってしまえば、あとは
だが、職場の安全管理もズサンだった当時は、労働も過酷をきわめていた。明日のために、とにかく眠ろうとするのだが、身体の節々が痛んでなかなか寝つけない。その痛む身体をさすっていると、なさけなくて涙が出そうになったことも、一度や二度ではない。
それでも、なんとか1か月間耐えて、厳しい肉体労働をこなすことができた。あらためて頑健な身体に産んでくれた母をありがたく思ったものである。
約束の集金日に会社を訪ねると、またしても問題が待っていた。なんと、経理係から渡されたのは、見たこともない約束手形であった。しかも、現金になるのは3か月先であるという。もはや言葉も出なかった。
しかし、こうしたアクシデントを体験したことで、かえって自信が湧いてきた。次の日からは、昼間の労働に変え、夜は夜で、知り合いに電話をかけ続けて、私にできそうな仕事をまわしてくれるように依頼した。
そんななかで、私は頭を下げることも平気になっていた。仕事に結びつくならば、なんの抵抗もなかった。ドモリで理系の私にしては、一大変身である。そして、徐々にであるが仕事一本に専念できるようになり、ほんとうの意味で独立したのだった。