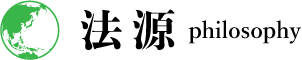第二章 是空
【9】
私の事業は、紆余曲折を経験しながらも、それをなんとか乗りこえて、しだいに拡大していった。加速がついてしまうと、あとは順風万帆である。どのようにやってもうまくいくのである。
そんな青信号ばかりの事業に、ついつい私は有頂天になってしまった。
自社ビルもでき、全国に営業所も設け、神奈川県に奇跡の会社誕生と新聞で紹介された。
その日の夕方のことである。ある紳士が会社へ訪ねてきて、あっという間に大きな商談が成立してしまった。その紳士のそつのない身のこなしに、私は「社長はこうでなければいけない」と、すっかりと感化されてしまっていた。ところが、それが手形の取りこみ詐欺だったのである。
気づいたときには、5億円の負債をかかえて会社は倒産してしまっていた。それからというものは、連日連夜のように債権者会議が続いた。会議の場へ顔を出せば、債権者の厳しい追求が待っている。しかし、私は逃げなかった。いや、正確にいえば逃げられなかったのである。ましてや、逃げる場所のあてもないし、逃げたからといって、何をして生きていくのかも思いうかばない状態だったのである。
結局、私はいつものように傷心した気持ちをかかえながら、会議場へ入るしかなかった。もちろん債権者からは、容赦のない罵声が飛んでくる。
「どうするんだ。どうするつもりなんだ。どう解決するんだ」
私はといえば、それに答える言葉をもちあわせていない。負債を清算する術もあてもない。ただ頭を下げ、債権者たちの罵声に、じっと耐えているしかない。震える拳を握りしめ、「すみません、私が甘かったのです」と繰り返すしかなかった。
明けても暮れても、毎日がその繰り返しだった。さすがに心身ともに疲れはててしまっていた。会議の夜、自分の部屋へ帰るにしても、まるで夢遊病者のように、ただ歩いているだけであった。
帰る部屋は、天井から裸電球一つがぶらさがった粗末な4畳半である。その裸電球がぼんやりと点った部屋の隅にすわって、考えることは一つだった。
「世間知らずの田舎者が、社長をやろうというのが間違いだった。世間というのはそんなに甘いものじゃないんだ」
いつもそれである。頭の中は、意味不明の言葉にもならない言葉が渦巻いている。考えているのか、考えていないのか、それすらしだいにはっきりしなくなっていた。ただ、ぼんやりと目に映る部屋を眺めている自分がいた。
いつのころからか、私の目は、部屋の隅にあるガス栓に向くようになっていた。なぜかガス栓が気になってしかたがないのである。まるで、ガス栓がなにかを語りかけてくるような気にさえ思えた。
「ひねれ、ひねれ、ひねれ」
ガス栓が語りかけるのか、私のなかのなにものかが囁くのか、私にはそう聞こえてくる。「ひねれ」という言葉は、私のなかを何度も駆けめぐった。その声にそそのかされ、本気でガス栓をひねる勇気はない。頭では「これをひねれば楽になれる。この苦しみと別れられる」とわかっていても、いざとなると実行する勇気が出てこないのである。
「俺にはガス栓をひねる勇気もないのか」
私は自分で自分の頭を何度も力まかせに叩いた。このまま割れてしまえばいいと、やけくそに叩いた。そのときの痛さは、いまでも忘れていない。
だが、そんな葛藤にも終止符を打つときがきた。混乱の