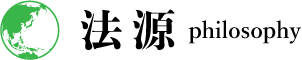第三章 天声
【4】
不思議なもので、「天声」の言葉は、そのときにおいては〝無理難題〟に聞こえてしまうことがある。しかし、時間の差はあるが、あるとき突然にして、その言葉の意味、言葉が指し示していることが一瞬にして解けることがあるのだ。
これが「天声」の特徴といえば特徴でもある。
「
この「天声」もしばらくは解けなかった。当時の私は、「天声」のものすごさは理解していたが、しかし、天声開説会での実証者の場合と違って、「
ある日のこと、税理士の行者さんが「会わせたい人がいる」といって訪ねてきた。
約束の場所は、帝国ホテルのロビーである。私は失礼があってはならないと、少し早めに到着していた。名刺などは持っていなかったので、その代わりにあの「
やがてその方が私の前の席に腰をかけられた。当時、大学教授であり宗教学者の中村先生であった。この出会いには、少し驚いたものである。
月並みなあいさつをすませ、これから雑談に入ろうとしていたときである。中村教授がテーブルの上に置かれた紙の束に興味を示され、
「それ、何ですか」
と聞かれた。私は内心ひやひやしながら、差し出した。
教授は、パラパラとめくっていたが、しきりに
「いったい全体、これはだれがつくられたのですか」
という。その本を綴ったのはたしかに私であるが、「つくれ」と示したのは天声である。そこで私はおもわず、
「天声です。すみません」
と答えた。どう考えても、「すみません」は余計である。会話のなかに、まだ成りきれていない自分がいた。中村教授はもう一度、念を押すように、
「天声って……。ほんとうにだれがつくったのですか。これはね、釈迦がいちばん説きたかったことがあらわれているんですよ。なにも書いてない紙が必要なんです」
と、そう言って、さかんにパラパラと白い紙の本をめくっている。今度は、私が面食らう番であった。
「それは、どういうことでしょうか」
すると、教授はわかりやすくていねいに説明してくれた。
「書いているものを読むだけでは、頭に入るだけである。ところが、なにも書いてないから、自分で書くしかない。書けば身につく。これが『行』というものなのですよ」
私は、ただ驚くばかりであった。
「それは……」
と教授は言葉を一瞬止めてから、さらにこう続けた。
「あるようで、ない。ないようで、ある。これが空の世界なのです。まさにこれは、釈迦が説きたかった世界の実体なのです」
私は、説明を聞きながら、誇らしさを感じていた。
「しかし、それをやらせたのは、天声なんです」
私は天声にしたがって「
「天声ですか……」
中村教授は、やや
「これこそ超宗だね。瞑想も写経も読経も超えたものだ」
と説明してくださった。私は、この言葉に、ハッと胸を突かれる思いがした。1月6日の「天声」が私のなかによみがえってきたのである。
「今の世は、科学、医学、政治、道徳、人為の宗教、何をもってしても救われない。いまこそ、大自然を造り動かしているそのものの力を天と定め、キリスト、釈迦についで、最後の救済者としての法源をこの世に送りだす」
私が「天声」で命じられた使命とは、この「超宗」だったのだ。
あらためて私は「天声」の奥深さに身震いし、自分のなかに「
別れぎわ、私は中村教授に「
この体験によって、私のなかの小さなわだかまりは消えた。そして、さらに「天声」のものすごさに気づかされていった。