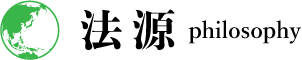第六章 救済
【2】
いま想えば、「天声」は当初から「救済の青写真」を示していたのだった。
天声村はもちろん「天声」で示され、その地に決まったのであるが、私と富士山の見える地との出会いは、すでに過去にあったのである。
28歳のころであろうか。私の興した会社も軌道に乗っており、順風満帆の毎日と思いこんでいたころのことである。そんなある朝のこと、私のまぶたに富士山の姿が、フッと浮かんだのである。
「そういえば、昔、一度登ったなぁ」
と、二十歳代の若い時代を懐かしく思い出していた。その日から毎日のように、暇さえあれば富士山の姿を思いうかべた。その
季節は初夏を迎えていた。その日は雨が降っていて、すそ野からではその姿をあおぐことはできなかった。私は一日だけ晴れるのを待ってみようと思い、すそ野周辺を時間つぶしに散策した。
茶の産地らしく、見わたすかぎりに茶畑が広がっていた。芽吹いた若葉には雨滴がコロコロと転がり、春が残した埃を吹きはらっていく。都会に住む私にとっては、そのようなことまでが新鮮に感じられた。
私は野宿をすることに決めた。その場所を探そうと、夕暮れの道を歩いた。しばらくすると、気に入った場所が見つかった。そこは茶畑のそばに大きな岩があって、そのすぐ脇からは清水が湧き出ていた。
雨はやんでいた。周囲は打ち水をしたように、すがすがしい雰囲気がただよっていた。私は夜を待ってから大地に横たわった。そして富士山麓の静けさに抱かれながら、いつしか深い眠りに落ちていった。
翌日は、快晴だった。さっそく富士山に登った。一歩一歩大地を踏みしめながら、しだいに小さくなっていく下界を眺めた。いつも感じることであるが、このような一歩一歩の積み重ねが自分を頂上に運んでくれるということの楽しさは、人生によく似ていると思うのである。
そしてまた、どのすそ野から登っても頂上は一つであるという事実である。それが何を意味しているのかわからなかったが、私はいつもそのような不思議な気分をかかえながら富士山に登っていた。
その後、私の生活は、ますます目まぐるしい日々となった。30歳で自社ビルを建て、それから4年後、独立して12年目に入ろうとするころに、倒産という体験を強いられた。そして、法源誕生を迎えたのだった。
法源としての日々は、夢中に過ぎていった。6年ほどすると、テレビの人生相談にレギュラー出演するまでになっていた。ラジオにも出演した。そして、その合間を縫うように、全国を行脚し、講演会を行っていた。
いまもそうであるが、毎日が
私はこの16年半、休みを頂いていない。1年365日、朝の
『天声聖書』を世に出したのもこのころであった。昭和55年1月6日から、昭和61年末までの「天声」を、私が記しておいた「天声ノート」から編纂した。
このころから、行者さんの輪が、目に見えるように広がっていった。そして、救済に立ちあがる人が多くなっていった。それまで見えなかったものが、「天意」によって地上へ形となってあらわされるようになってきていた。
そのように勢いが増してくると、それに比例するようにまわりも騒がしくなってくる。マスコミに紹介されたかと思うと、そのマスコミが掌を返したように、まるで罪悪人のように叩いてくる。とにかく持ちあげられたり、落とされたりと、振りまわされることばかりが起こった。
さらに、私をただの宗教家と勘違いして、いろいろな人がさまざまな企画を持ちこむようになってくる。これには
そうしたある夜のこと、
「地上に人間天国を残せ。救済のメッカ・天声村を築け」
との「天声」が下った。その地こそ、
さっそくスタッフによって、候補地捜しが始まった。ある程度絞られたので、私は2、3か所の候補地へ実際に赴いてみた。はじめの候補地は、どうも
それではということで、最後に案内されたところが富士山の麓であった。着いてみると、かすかではあるが見覚えがあった。周辺の様子は少し変わっていたが、まさしく14年前に野宿したその地であった。
あのころは、まさか会社が倒産するとは夢にも思わなかったものである。その土地は依然として昔のままであるが、私は変わっていた。ただ不思議な縁というか、このような形でふたたびこの地を訪れるとは、思いもよらないことであった。
巨岩も清水も、そのまま残っていた。まるで14年間をじっと待っていてくれたような気がしてならなかった。
後日、「天声」は、いくつかの候補地のなかから、その土地を指した。まるで私の人生の道のりが、ここに到達するためにあったように感じた。どれを取ってみても、偶然のようで必然的な結果となっているからである。
しかし、そのようなことはどうでもよかった。この地を天声村に指定してくれたことに、私は感激もひとしおであった。ちょうど、法源誕生の7年目のことである。